AFP通信がぞっとするような見出しのニュースを3月9日に配信した。その見出しは「ディーゼル車の二酸化窒素で6000人死亡、ドイツ政府報告書」というもの。いったいこれはどういうことなのか、調べてみたもののシックリする答えが見つからない。
そこで今回はメカニズムに詳しい鈴木直也氏にこの発表の真意と、本当にディーゼル車の排ガスで6000人の命を奪ったのか聞いてみた。意外にも内容のあるレポートだったようだ。
文:鈴木直也/写真:Shuttestock.com
■二酸化窒素で人が死ぬ!! それはどういう意味?
AFPが配信したニュースが話題を呼んでいる。見出しタイトルは「ディーゼル車の二酸化窒素で6000人死亡、ドイツ政府報告書」というもの。これだけ読むと、どこかで人がバタバタ倒れて死んでいるかのような過激な表現だ。
ただし、詳しく見てゆくと、もちろんそんな激甚災害みたいな話ではない。内容を要約すれば、「心疾患で死亡した約6000人について、元をたどれば大気中に排出されたNO2(二酸化窒素)が原因だった可能性がある」というもの。
しかも、「死亡」の中身も、正しくは「標準より早死にしている」が正解。まさに羊頭狗肉。炎上狙いの大げさな表現と言わざるを得ない。ふつうの人は、「NOx(NO2を含む窒素酸化物)で人が死ぬ」と言われれば、NOxが人体に害を与えて病気になって死ぬと考える。
タバコと肺がんの関係みたいにわかりやすい疾病メカニズムであれば、それは「因果関係がある」と結論づけてもいいだろう。
そうなると、NOxの人体への影響について、タバコのように広範な医学的研究、あるいは疫学調査があるのかが知りたいポイントだが、このニュースの元となったドイツ環境省の声明文や、そこに記載されている統計データなどのリンクを調べてみても、因果関係についての論文などは見つからなかった。
まぁ、考えてみれば、日常的のどの程度のNOx濃度の大気を呼吸しているかは、それこそ一人一人すべて違うし、身体に変化が生じるほど長い期間にわたって、呼吸した大気のNoxレベルを調査記録し続けるなんていうのは非現実的。
NOxが生物にもたらす影響については動物実験などで研究可能だが、一般人を対象とした疫学調査でNOxがもたらす健康被害の因果関係を立証するのは、誰が考えてもかなり難しいと思われる。




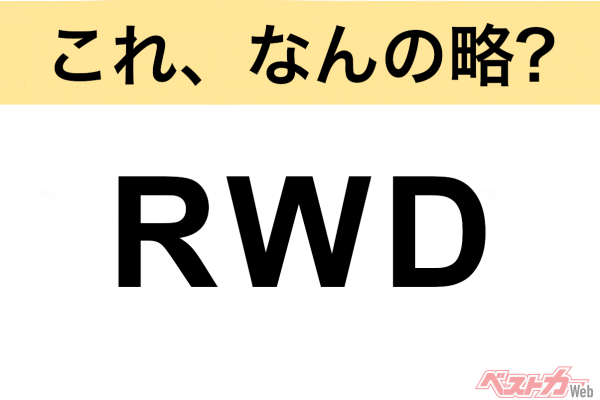














コメント
コメントの使い方