JMS2025のプレゼンテーションに登壇した豊田章男会長は、センチュリーへの想いを吐露した。「日本を元気にするためにセンチュリーという『ブランド』を立ち上げる」と語った豊田章男会長の狙いはどこにあるのだろうか?
※本稿は2025年11月のものです
文:ベストカー編集部/写真:トヨタ、ベストカー編集部
初出:『ベストカー』2025年12月26日号
豊田章男会長と「センチュリー」
豊田章男会長は社長時代「センチュリーは名誉会長のクルマなんです」と語り、自らはセンチュリーに乗ろうとしなかった。
名誉会長とは父である豊田章一郎氏のことだ。1967年誕生の初代、1997年の2代目、そして2018年の3代目と、3代にわたってセンチュリーの開発に携わり、愛車として乗り続けた豊田章一郎氏のセンチュリーへのこだわりを見聞きし、畏怖のような気持ちもあったように思う。
その一方でセンチュリーは変わらなければならないと豊田章男会長は考えていた。2019年の箱根駅伝ではセンチュリーGRMNをつくり先導車として公開した。
そして、2023年会長になったタイミングで、新しい世代の新しい考え方を持ったお客様に新しいセンチュリーを届けたいと、SUVのスタイルをしたセンチュリーを発表した。
そのセンチュリーは、豊田章男会長が「ボクが乗っていいセンチュリーを提案してください」と開発陣に話し、生まれたものだと明かしている。
さらに2024年の大相撲初場所では、優勝力士のパレードカーとしてセンチュリーのオープンを相撲協会に貸与した。
いずれも豊田章男会長が新たに解釈した新しいセンチュリーの提案だった。
そして、2025年のジャパンモビリティショーで大きな決断を発表した。センチュリーをトヨタブランドの最高級車から、独立したブランドに育てていこうというのだ。
伝統を重んじながらもセンチュリーのあるべき姿は時代とともに変わる。センチュリーには、ほかのクルマにはない求心力がある。ならば、その力を使って新しいものを生み出していけるのではないか? 豊田章男会長ならではの発想だ。
なぜ初代センチュリーが必要だったのか?
初代センチュリーは1967年に誕生しているが、開発は1963年から始まっている。
当時のトヨタは日本国内の乗用車販売で30%を超えるシェアを獲得していたが、海外メーカーのような伝統や革新性をもったメーカーと見られているわけではなかった。そんな時代になぜセンチュリーをつくろうとしたのか?
初代センチュリーはトヨタ初の主査となった中村健也氏が主査を務めている。中村氏は「日本人の頭と腕で、日本に自動車工業をつくらねばならない」と国産車づくりに情熱を傾けたトヨタ自動車の創業者である豊田喜一郎氏に憧れ、自ら手紙を書いてトヨタに入社した。
中村氏は「開発は度胸」と語り、「俺のクルマ」を作りなさいと部下に教えた。自分がいいと思えば、周囲の反対も押し切った信念の人だった。
クラウンやコロナといった革新的なモデルを世に送り出した後に手がけたのがセンチュリーだ。そして、技術担当役員としてセンチュリーの開発を後押ししたのが豊田章一郎氏だ。
1960年代は高度成長の時代だ。国民の所得が大幅に増加し、モータリゼーションの波が訪れた。「マイカー」という言葉がもてはやされたが、一方で官公庁や大企業の公用車はアメリカ製の大型乗用車が使われていた。
中村健也氏は「同じではダメだ。どんなクルマとも違う高級車をつくるんだ」という強い想いを持っていた。
豊田喜一郎氏の夢だった国産車はつくれるようになった。しかし、日本人にしかつくれない高級車をつくることで、初めて、日本とトヨタが世界に自動車メーカーとして認められる、そんな想いが中村健也氏にも豊田章一郎氏にもあったのだと思う。
戦後から20年近くが経ち、復興も進み、経済的にも豊かになった。今こそ日本人が得意としたモノづくりの精神によって、日本人がプライドを再び持てる工業製品が必要だと考えたのだ。
豊田章一郎名誉会長が亡くなったあと、センチュリーのことを誰よりも学び、深く知ろうとしたのが豊田章男会長だ。
60年以上前の中村健也氏と豊田章一郎氏が思い描いた「同じでないもの」をつくるスピリットに共感し、今こそ新しいセンチュリーをつくり、日本を元気にしたい。もっと言えば、センチュリーでやらなければならない。
その想いを「日本から『次の100年(センチュリー)をつくる』挑戦」と豊田章男会長は表現した。
センチュリーブランドをつくることはクルマだけではない、「日本の文化を世界に発信すること」を含めたものなのかもしれない。そう考えると日本自動車会議所の会長に就任した際に「クルマをニッポンの文化に」と「宣言」したことともつながってくる。















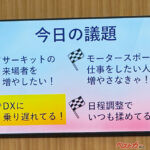
























コメント
コメントの使い方