クルマのよさを評価するのにはたくさんの要素が必要。デザイン、エンジン、トランスミッション、インテリア、など多くの要素が複雑に絡み合っていることで、一台のクルマの完成度が決まる。
特に足回りのダンパー、サスペンションなどは評価軸として非常に重要なファクター。マルチリンクでもトーションビームでも、FRでもFFでも、「後ろ足」の動きもよくないとダメなんです。
そこで5人のジャーナリストが唸った「後ろ足」のいいクルマを挙げてもらいました。スポーツカーだけではないその選考から見ても、「後ろ足」の重要性というものがおわかりになるかと思います。
文:松田秀士、斎藤聡、桂伸一、国沢光宏、片岡英明/写真:ベストカー編集部
ベストカー2017年11月10日号「クルマは”後ろ足”で変わる!!」
■本格スポーツカーではやはりこの2車種!!
【国沢光宏選 シビックタイプR】
「後ろ足がダメなクルマ」は多数存在してきた。一番アカンのが「頑張れるだけ頑張り、限界超えたらコントロールできなくなるほどシビアな挙動になる」とい うもの。
典型例は初期のNSXや初代プリメーラ。リアが流れ出したら、もはやお手上げ。ヘタに立て直そうとしてタコ踊りするより、フルブレーキ踏んでスピ ンさせるしかない。
逆に「後ろ足のいいクルマ」ってわかりにくい。後ろ足のグリップが前より高いだけなら、コーナーでアンダーステアとなりツマらんクルマ になる。
ということで「後ろ足のいいクルマ」=「コーナリングバランスよくコントロール性の高いクルマ」と言い換えてもよかろう。
もう少 し掘り込めば「同じクラスのライバルより高いコーナリング速度を確保した上、アクセル開けた時のアンダーステアが少なく、アクセル戻したりブレーキ掛けて 後輪荷重抜いた時は、意のままに曲がろうとする」特性。
最近のクルマで「超いいね!」したのが、新型シビック タイプRである。バランスいい。
ホンダ鷹栖のテストコースは、1G近い横G掛かっているコーナーの途中に、タイヤが路面から離れるようなギャップを作っているのだけれど、そこを通過した 時の前後バランスときたら見事である!
よくセッティングされたラリー車の如く、ドライバーの眼球を揺すり、視界が怪しくなるほどの激しい挙動を出しなが らも、車体の姿勢変わらない。
タイトコーナーはブレーキで荷重移動させてやると、ドライバーの意のままに姿勢を作ることだって可能。すばらしい後ろ足だと 思う。

【片岡英明選 WRX STI】
1980年代、ベンツ190Eのリアサスに魅せられた。それからはマルチリンクの魅力に取り憑かれ、R32スカイラインのコントローラブルさには感激の声をあげたものだ。
最近のクルマは完成度が高く、サスペンションだけでなくタイヤもいいからリアサスの魅力がわかりづらい。
久しぶりに感激したのが、WRX STIタイプSのリアサスペンションだ。ご存じのようにタイプSはビルシュタイン製ダンパーを装着している。夏にマイナーチェンジを行ったが、このときに 足まわりに手を入れ、減衰力の最適化を図った。
フロントストラットのスプリングレートを下げ、リアのスタビライザーは径を1mm細くして いる。
この結果、ステアリングを切った時に気持ちよく鼻先が向きを変えるようになった。旋回している時にアクセルを踏み込んでも外側に大きくはらむことが なくなり、鼻先は軽やかに向きを変える。感激するくらい舵の入りがいいのだ。
可変差動制限機構のマルチモードDCCDが装備されているか ら当然だ、という人もいるだろう。
確かに味付けが変わったことによりプッシュアンダーが減り、狙ったラインに乗せやすくなった。が、リアサスが滑らかに動 くようになったから気持ちよく向きが変わり、優れたトレース性も実現しているのだ。
スムーズにクルマの向きが変わり、荒れた路面でもしたたかな接地フィー ルを見せつける。安定しているだけでなく操っている感も強い、走り屋好みのリアサスペンションだが、不快な突き上げも上手に抑え込んでいる。


















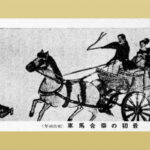



コメント
コメントの使い方