自動車業界は100年に1度の大変革期にあるそうで、内燃機関から電気への転換をどうすればいいのか、蜂の巣を突いたような大騒ぎになっている。
長期的に見れば自動車の動力源が電気にかわってゆくのは必然で、少なくとも専門家でそこに異論のある人はいない。
しかし、お正月の一般社団法人 日本自動車工業会(自工会)のTVCMで話題になったとおり、日本には自動車関係の仕事に携わっている人が550万人もいる。2030年代には内燃機関だけで走るクルマを全廃しようという動きがあるけれど、雇用や軽自動車の問題など、きちんとした移行プロセスについての議論はまだこれから。問題は化石燃料から電気への移行をどうスムーズに軟着陸させるかなのに、そこがスコーンと抜けているのだ。
欧州ではCO2削減=EVみたいな風潮だが、目的はEVを増やすことではなくCO2の削減だよね?
だったら、ぼくは今あるリソースを有効に使うべきだと思う。日本には高効率なプラグインハイブリッド技術があるんだから、それを活用しない手はない。
で、そんな時まっ先に思いつくのがこのクルマ、三菱『エクリプスクロスPHEV』だ。
ガソリンと電気を効率よく使い分けるPHEVで「東日本大震災から10年の節目に被災地を巡り、あわせて日本のエネルギー問題を考えるドライブ」に出かけてみよう。それがこの企画の趣旨だ。
東京都文京区から岩手県陸前高田市まで片道約510km(往復1020km)を走って、SUV+PHEVのその実力をしっかり試してきた。
※取材日は2021年1月下旬。2021年2月13日に発生した、福島県沖を震源とする地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。同日夜には、関東地方と東北地方の各所に大規模な停電が発生しました。
当編集部としましては、改めて、大規模災害とともに暮らさざるをえない日本の現状と、その「備え」の選択肢のひとつとして、電源として広く活用できる大容量バッテリーと高い走破性を併せ持つ「SUV+PHEV」が用意されていることについて、考える機会となりました。
文/鈴木直也 写真/奥隅圭之【PR】
【画像ギャラリー】震災から復興が進む「奇跡の一本松」など東北の今 そしてエクリプスクロスPHEVの魅力を知る!!
■震災から10年の東北へ 電動化社会でのPHEVという賢い選択
さて、そもそもPHEVの何が嬉しいかというと、電欠を気にせずEVの美味しい部分を味わえるところ。エクリプスクロスPHEVのEV航続距離はWLTCモードで57.3kmと、PHEVの中でもトップクラス。まずはその実力を確認すべく、EVプライオリティモードにセットして西神田ランプから首都高経由で常磐道を目指す。目的地は宮城県石巻市だ。
平日の午前中は都心に向かう上り線の渋滞がひどいが、下りはいたってスムーズ。あっという間に三郷ICを過ぎて常磐自動車道に入る。ここまで完全なEV走行を続けているが、容量13.8kWhのリチウム.・エナジー・ジャパン製リチウムイオン電池は昨晩のうちに編集部でフルチャージしておいたから、まだ容量は半分ぐらい残っている。
それにしても、EV走行時の静粛性の高さは大したもの。エンジン騒音がなくなると普通はタイヤから上がってくるロードノイズが気になるものだが、エクリプスクロスPHEVはそのあたりの遮音がじつに巧み。今回の試乗車がスタッドレスタイヤを履いていた点を考慮すると、なおさらその優秀さが際立つ。
音羽のベストカー編集部から100%EV走行で守谷SA付近まで到達。このあたりでトリップメーターはほぼ50kmに達したが、メーター上のEV走行可能距離はまだ20km近く残っている。空いた高速道路をほぼ法定速度で走るという好条件なら、WLTCモードで57.3kmというカタログ値を超えて、70kmくらいまでEV航続距離を伸ばせそうな感触だ。
谷和原インターを過ぎたあたりでEV走行可能距離は10kmを切っていたが、ふと気がつくとエンジンが始動してハイブリッドモードの走行に切り替わっている。
自分でアクセルを踏んでいたにもかかわらず、音楽を聴いていたためか迂闊にもそれに気づかず。ぼくの注意力が散漫だったのは認めるけど、エクリプスクロスPHEVのエンジンはそのくらい存在感を感じさせず静かに回るのだ。

初期型アウトランダーPHEVのエンジン排気量は2Lだったが、2018年のマイチェンで2.4Lに変更。これがそのままエクリプスクロスPHEVにも搭載されている。
このエンジン排気量拡大はパワーアップという意味ではなく、低速トルクの厚みを増してエンジンがかかっているときでもなるべく低い回転数で発電機を駆動したいから。アウトランダーに乗った時にも感心したのだが、エクリプスクロスPHEVもエンジン始動時のノイズレベルは低く、高速クルージング時にはほかの騒音に紛れてほとんど目立たない。
初期型アウトランダーPHEVでユーザー調査を行ったところ、EV走行中にエンジンがかかるとがっかりするという声が多かったという。そういう意味では、排気量を拡大して常用回転数を下げたのは大正解。アクセルをガバッと踏んだ時くらいしか存在を主張しない。そう言っていいほどエンジンは黒子に徹している。
これ以降はクルーズコントロールを100km/hにセットして巡航する。電池は使い果たしたけれど、マルチインフォメーションディスプレイの航続可能距離はまだ500kmオーバー。もちろん、これはタンクに入っているガソリンの量から計算されたものだが、この辺の安心感がEVとPHEVの決定的な違い。今日の目的地である石巻まで片道約400kmだが、それを余裕でカバーする足の長さがある。
出発から約200km走っていわき中央ICを過ぎると、めっきり交通量が減ってくる。ここから先は東日本大震災で大きな被害を受けた区間でもあり、福島第一原発の廃炉処理が行われているエリアでもある。道路は上下1車線の対面交通となり、行き交うクルマも復興関連の工事車両がほとんどだ。
2019年のデータによると、再生可能エネルギーや原子力発電などCO2フリーな電力の割合は約25%にとどまる。
これでは政府が掲げた2050年カーボンニュートラルには全然届かないから、資源エネルギー庁は2030年度までにCO2フリーの電力を44%まで増やす目標を掲げている。原発33基のうち現在稼働中なのは関西方面の9基のみだが、カーボンニュートラルを実現するには休止している原発の再稼働を検討せざるを得ないという計算だ。
いまだ復興途上の常磐富岡ICから常磐双葉ICあたりを走りつつ、カーボンニュートラルと簡単に言うけれど、本当に地球環境を大切に思うなら我々一般人もエネルギー問題を他人事としていてはいかんなぁ。そんな思いを強くした。


仙台空港ICを過ぎると石巻まであと50kmほど。この辺からチャージモードに入れて走行用バッテリーの充電を開始する。
PHEVは電源プラグに繋がなくても走りながらバッテリー充電できるのが利点。高速を30分も走ればほぼ8割がたチャージが可能だ。もちろん、充電に使ったぶん燃費は落ちるが、そのかわり高速を降りた下道をEVモードでスイスイ走行可能。ガソリンと電気は適材適所だが、その使い方を臨機応変に選択できるのはとても賢いと思う。
■経験者の声から知った 災害に強いクルマの重要性
そうこうするうち石巻市に到着。ここでは宮城三菱自動車販売 石巻店に立ち寄り、東日本大震災当時のお話を取材させていただく。
インタビューに応じていただいた販売課長の松林政雄さんによると、地震が起きた瞬間はディーラー店舗内で勤務中だったそうで、長時間の揺れと何度も繰り返す余震にかつてない恐怖を感じたという。

「建物が築4年と新しかったためか、店舗にほとんど被害がなかったのは幸運でした」
停電で情報も混乱していたため、震災当日から4、5日は休業状態だったそうだが、やがてディーラー店舗にお客さんからの連絡が入りはじめる。
「水に浸かったクルマを修理できないか。あるいは中古でなんでもいいからクルマが手に入らないか。そんな問い合わせが殺到しましたね」
結局、「震災対応には半年以上かかりましたねぇ」という状況だったのだそうだ。
松林さんによると「いちばん難儀だったのは停電がなかなか復旧しなかったこと」だそうだが、今ならエクリプスクロスPHEVからV2H機器経由で店舗や家庭に給電が可能。ガソリン満タンなら一般家庭の使用で約10日間、電源車として使うことができる。

災害時の電動車活用については、経産省と国交省が促進マニュアルを整備しているが、三菱自動車としても「DENDO コミュニティサポートプログラム」として、電動車を速やかに被災地・避難所などへ提供できる体制づくりを目指している。東日本大震災という未曾有の大災害を体験したことで、現地ではそれがよりリアリティをもって実感されているようだった。
※2021年2月15日に、「DENDO コミュニティサポートプログラム」において、100の自治体と災害時協力協定を締結したことを発表。災害発生時に時間のロスなく、給電等に活用できるプラグインハイブリッド電気自動車を貸し出すことができる体制ができ上がっている。


●災害時の支援体制強化に取り組む三菱自動車が100の自治体と災害時協力協定を締結
●全国100以上の自治体が認めた三菱のPHEV その活動の詳細はコチラ
■震災復興の象徴「奇跡の一本松」へ どんなシーンでも頼れる一台
この日は石巻で一泊し、翌日は東日本大震災からの復興が進む陸前高田市を目指す。そう、「奇跡の一本松」で有名になったあの海岸だ。
石巻から陸前高田までは三陸自動車道が通じているが、高速をちょっと手前の気仙沼中央ICで降りて一般道を走ってみる。
リアス式海岸をなぞるように走る国道45号線は、カーブとアップダウンの多い海沿いの一般道。路面は決してスムーズとはいえないが、エクリプスクロスPHEVは快調に走る。
エクリプスクロスPHEVの走りの醍醐味といえば、低重心がもたらす安定したコーナリングフォームとS-AWCによる安定した4輪のトラクション制御だが、もうひとつ忘れちゃいけないのが、しなやかな足回りがもたらす良質な乗り心地。モーター駆動ならではのトルクフルな走りと相まって、日常的な足としても使い勝手が抜群にいい。
クルマが陸前高田市に近づくと、まず目に入ってくるのは巨大な防潮堤だ。4年前に完成したこの巨大建造物は、高さ12.5m、全長約2kmというスケール。震災前にあった高さ5.5mの防潮堤が津波で全壊したことを考慮し、高さを倍以上にかさ上げするとともに台形断面のより強固な構造を採用、11.5mクラスの津波に耐える設計だ。
防潮堤の向こう側には、かつて高田千本松原と呼ばれた美しい松林が広がっていたが、その姿を取り戻すべく新たな松の植林も進められている。

防潮堤の内陸側には復興祈念公園が整備され、その一角には移植された「奇跡の一本松」や道の駅とともに「東日本大震災津波伝承館」が建設された。
取材を兼ねてわれわれも見学させていただいたが、あの地震と津波の被害のすさまじさを再認識するとともに、こういう悲劇を繰り返さないためにわれわれは何をすべきか、自分なりに大いに考えさせられるものがあった。
東日本大震災から10年を経て、被災地のインフラは着実に復興しつつあるが、そこに暮らす人びとの生活再建はまだ道半ば。工事用車両やクレーンなどが姿を消して町が以前の落ち着きを取り戻すには、まだしばらくの時間が必要だし、なにより経済が回るようにならなければ人びとの日常は戻ってこない。
これは、いま話題となっているカーボンニュートラル政策も同様。CO2削減には産業構造の転換が不可避だが、きちんと経済を回しつつ自動車産業やエネルギー産業の構造を変えて行くのは容易なこっちゃない。
何が言いたいかというと、500万円とか1000万円もするEVだけで世の中を変えることはできないってこと。本気でCO2削減に取り組むなら、コストパフォーマンスがよく使い勝手のいい環境車こそが重要なのだ。
そう考えると、エントリー384万8900円からというエクリプスクロスPHEVのコスパの高さはすごい。

補助金などのインセンティブを付けないと売れないんじゃサステイナブルとは言い難い。キモは普通のユーザーが欲しいと感じる利便性と現実的な価格。カーボンニュートラル政策にリアリティを感じさせるのは、エクリプスクロスPHEVみたいなクルマだと思う。
■価格とグレード(PHEVモデル)
・P(4WD):447万7000円~
・G(4WD):415万2500円~
・M(4WD):384万8900円~
■エクリプスクロスPHEV 主要諸元
・全長:4545mm
・全幅:1805mm
・全高:1685mm
・ホイールベース:2670mm
・最低地上高:185mm(ガソリンモデルは175mm)
・車両重量:1900~1920kg
・エンジン:直4DOHC
・総排気量:2359cc
・最高出力:128ps/4500rpm
・最大トルク:20.3kgm/4500rpm
・モーター(前):82ps/14.0kgm
・モーター(後):95ps/19.9kgm
・ハイブリッド燃料消費率 WLTCモード:16.4km/L
・EV走行換算距離:57.3km
■取材協力
・宮城三菱自動車販売 石巻店
宮城県石巻市恵み野3丁目1番地4
0225-96-4055
月~土 9:30~18:30、日・祝 9:30~18:00(定休日 水曜日・第二火曜日)
・東日本大震災津波伝承館
岩手県陸前高田市気仙町字土手影180番地(高田松原津波復興祈念公園内)
0192-47-4455
開館時間 9:00〜17:00(最終入館16:30)















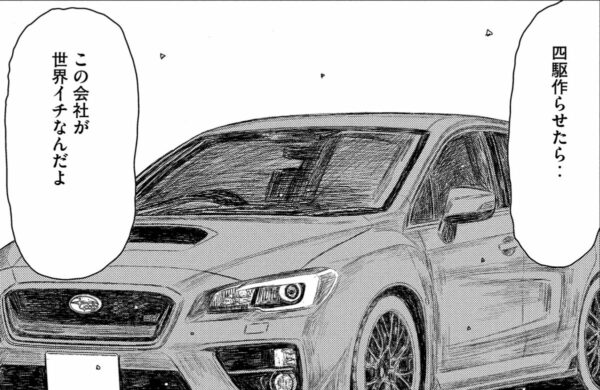



















コメント
コメントの使い方