いまやスポーツカーも含め多くのクルマにハイテク装備が満載されて、かつてはドライバーが行なっていた操作をかわりにやってくれる機能も増えてきたが、昔はクルマを上手く操るための裏ワザ的な運転テクニックがいくつも存在した。
その中から、クルマ好きなら必ず耳にしたことがあるであろう代表的な例をいくつかピックアップしてみた。
おそらく読者の多くのみなさんの中でも、たとえモータースポーツをたしなんでいなくても、やってみたくてしょうがなくてチャレンジした経験のある人も少なくないことだろう。
それらの運転テクニックは、はたして令和を迎えた今の時代でも必要なのか? やって効果はあるのか? もはや死語になってしまったのだろうか…!?
文:岡本幸一郎/写真:MAZDA、TOYOTA、NISSAN、ベストカー編集部
ダブルクラッチ
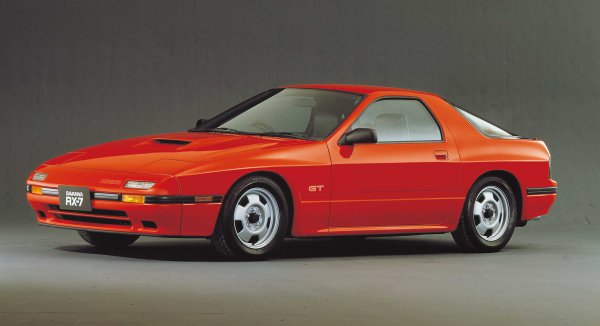
MT車でシフトチェンジする際に、クラッチを切ってギアをニュートラルにし、一度クラッチを繋いでニュートラルのまま必要に応じてアクセルを踏んでエンジン回転数を上げ、もう一度クラッチを踏んでみギアを入れてクラッチを繋ぐという、1度のシフトチェンジで2回クラッチ操作を行なうというテクニック。
これは現代のMT車にはごく普通に付いているシンクロ機構の役割を人間の操作で行っていたというべきもので、現代ほどシンクロ機構がよくなかった時代、スムーズにシフトチェンジするためにはやったほうがよいとされた。
現代のクルマは一度だけクラッチを踏んだ間にスムーズにシフトチェンジできるので実質的に必要なくなったといえるが、たとえシンクロが付いていても機構的にはダブルクラッチを行なったほうが、よりミッションに負荷をかけないことには違いない。
暖機が充分でないなどの理由でシフトが渋い場合にもダブルクラッチをやれば入るケースも多い。覚えておいて損はなく、できるならやったほうがよい。

ヒール&トゥ
MT車(マニュアルシフト可能な一部AT車も含む)で、減速してシフトダウンする際に、右足のトゥ=爪先でブレーキを踏みながら、ヒール=かかとでアクセルをあおってエンジン回転を上げてやることで、エンジンとギアの回転数を同期させてスムーズにシフトダウンしてクラッチミートできるようにするテクニック。

モータースポーツでは今でも当たり前のように行なわれており、公道でもちゃんとできればトランスミッションにかける負荷が小さくなるだけでなく、同乗者から見てもカッコイイし、エキゾーストサウンドを聞いても気持ちがよいものだ。
ただし、ブレーキの踏力を変えることなく右足で同時にアクセルをふかすという操作は、慣れないとなかなか難しい。
最近ではエンジンとギアの回転数を自動的に同調してくれる機構を持つクルマが増えてきており、だんだん不要のテクニックになりつつある。























コメント
コメントの使い方