人生の潤いには映画のような作品に触れて感動し、また触発されるという経験が非常に有用だ。
そして映画には、その映画毎ごとにキーとなるアイテムがあり、その対象にクルマが選ばれることも多い。
今回はそんな、重要なキーにクルマが選ばれた作品について、どんな映画か、またどんな効果が生まれているか解説した。これらの映画を見ると、登場しているクルマが欲しくなってくるかも?
文/渡辺麻紀
写真/サーブ、BMW、プジョー、オースチン
■1台のクルマから人生と主人公たちの想いを連想させてくれる
ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』がアカデミーの国際長編映画賞のみならず作品賞をも獲得し、韓国映画のパワーを見せつけたのが2019年。もしかしたら今年、日本映画でも同じことが起きるかもしれないといわれているのが『ドライブ・マイ・カー』だ。
濱口竜介監督が、村上春樹の短編を映画化し、すでにカンヌ映画祭をはじめ、世界の各映画賞に輝いている作品である。
タイトルからもわかるように、本作では「クルマ」が重要な意味をもっている。原作では黄色いサーブ900のコンパーチブルが、映画では赤いサーブ900に変更されているが、主人公はそのクルマを、あたかも自分の聖域のように扱っていて、クルマと彼の人生が強くコネクトしていることが伝わってくる。
今回、紹介してみようと思うのは、その『ドライブ・マイ・カー』のように1台のクルマからさまざまな人生や、キャラクターたちの想いを連想させてくれる映画。移動の手段であることはもとより、アクションをより迫力あるものにするためのアイテムでありつつ、主人公、あるいは監督のこだわりや人生を感じさせてくれる映画だ。
■ラスト・ランの美しいラスト
そんな映画としてまず、最初に挙げたくなるのが『ラスト・ラン』(1971年)。公開時は原題と同じこれだけだったが、DVD化された時からなのか『ラスト・ラン 殺しの一匹狼』とサブタイトルが加えられていた。
とはいえ主人公は殺し屋ではなく逃がし屋。すでに引退し、ポルトガルの港町でひとり余生を送っている。そんな時に若い金庫破りから仕事を頼まれ、愛車である8気筒エンジン搭載の1956年型BMW503コンバーチブルを走らせることになる。
クルマファン的に嬉しくなるのは冒頭。主人公のガームス(ジョージ・C・スコット)がBMWを整備しているシーンから始まるのだが、この整備が本当に丁寧で優しく、そこからクルマへの愛情のみならず、彼の生き方まで伝わってくる。
ギャングが放った白いジャガーとのチェイスアクションも用意されているものの、それでも印象に残るのはBMWを愛でるガームスの姿。そんなアクションのあとに用意された、彼とクルマの関係性を凝縮させたラストがあまりにも美しいからだ。
彼の車愛で幕を開けたこの映画は、両者の強い結びつきを感じさせるシーンで終わる。これはクルマファンならたまらないラストだと思う。
ちなみにBMWのタイプには1957年型、1958年型、1959年型説もあるが、1956年から1959年までBMWが作ったコンバーチブルはわずか139台だったというから、かなりレアなクルマであることに間違いはない。だからこそ愛情をかけた、ということなのだろう。
余談ながら、筆者の父親はこの映画を観ていたく感動し、それまで国産車を買い換えながら乗っていたが、ドイツ車に乗り替え、それからクルマを運転できる間はずっと、まるでガームスのように愛情を注ぎながら乗り続けていた。この映画は、そういう意味でもスペシャルな思い出を残してくれたのだ。














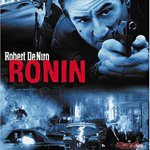

























コメント
コメントの使い方