■ガソリンスタンド
EVの増加によりガソリンスタンドはその数を減らす。とはいえ、今後9年でエンジンを搭載するクルマが急になくなるわけではないので、存続はしていく。
EVの急速充電器を備えるガソリンスタンドも増えるが、それ以上にガソリンスタンドとコンビニといった形態も増えていくだろう。
地方ではショッピングモール内にガソリンスタンドを設置する例などもますます増加する。大型カー用品店との併設も増える。ガソリンスタンド専業というのは難しい時代がやってくる。
また、現在はレギュラーガソリン、ハイオクガソリン、軽油という3種の燃料をそれぞれ別のタンクに貯蔵するため、輸送も貯蔵もコストがかかる。
これをレギュラーガソリンのオクタン価を欧州ミドルレギュラー並みの95にアップし、それ以上のオクタン価が必要なモデルについては給油時に添加剤がポンプで混合されるようにすれば、輸送、貯蔵ともにコストダウンが可能。タンクの検査費用も3分の2となる。そうした工夫が必要になっていく。
(TEXT/諸星陽一)
■カーナビ
結論から言うとカーナビ自体はなくならない。ただし、これまでの「商品」としてではなく「機能」としての存在にシフトしていくはずだ。
昨今の純正ナビはインテリアのデザインに合わせた専用設計が当たり前になっているが、今後は単なる案内機能だけでなく、情報を統合してドライバーへの安全や環境性能を高める機能、さらに言えば自動運転領域での活用も考えると従来とは比較にならないほど性能向上が求められる。
ただ、世の中にはそれまで販売されてきた多くの車両が存在するわけで、それらには後付けで先進機能を装着することは難しい。
つまり、従来までの2DINに代表される取付スペースを持つクルマに関しては市販やディーラーオプションのAV一体型ナビ、そして徐々に勢力を拡大しているディスプレイオーディオがまだまだ市場を牽引しているはずだ。
そして重要なのは2030年には実現しているであろう通信革命だ。5Gは当たり前、100Gbpsという驚異的な通信速度を持つ「6G(仮称)通信」がクルマにおけるIoTを激変させるだろう。
速度のほか、マルチタスクを可能にする多重接続や5G以上に通信電波が届く特性が実用化されればAIを活用しすべてのクルマを集中管理してナビ誘導してくれる世界も充分考えられる。
(TEXT/高山正寛)
■カーシェアリング
カーシェアリングは都市部を中心に発展してきたが、今後は郊外にもその勢力を伸ばす。今回の新型コロナウイルスまん延によって、在宅勤務が増加し、郊外への移住が進む。そうした人の動きによって郊外でのカーシェアリングが伸びていく。
従来はコインパーキングなどを利用したカーシェアリングステーションが主流だったが、今後新しく開発される住宅地ではインフラのひとつとしてカーシェアリングステーションが設けられるだろう。
新たに作られるカーシェアリングステーションはEV専用、もしくはEVをメインとしたものとなり、普通充電器と急速充電器を装備。
通常駐車時は普通充電器付きの駐車枠に止める。利用者はスマホアプリで充電状況を確認しつつ利用するクルマを選ぶ。充電量が少ないクルマは、敷地内にある急速充電器を使っての充電も可能だ。
普通充電器はカーシェアリング専用となるが、急速充電器は一般客も使用できるようになっているだろう。
(TEXT/諸星陽一)




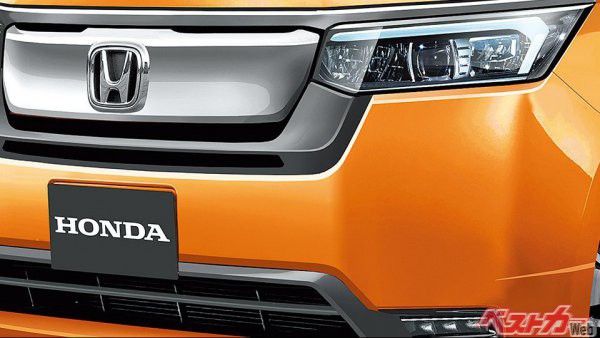


















コメント
コメントの使い方