クルマの購入といえば、昔ならディーラークレジットで分割払いが定番。某ロックスターの伝説のように現金一括で買ったというツワモノも少数ながらいるだろうか。
最近ではクルマの入手方法も多様化してきた。ここではスマートフォンの販売にも取り入れられている「残価設定ローン」と、ネットサービスに倣った「サブスクリプション方式」を取り上げ、それぞれの違いやメリット、賢い使い方などを解説する。
※本稿は2022年3月のものです
文/渡辺陽一郎、写真/AdobeStock、ベストカー編集部 ほか(トップ画像=SRT101@AdobeStock)
初出:『ベストカー』2022年4月10日号
■残価設定ローンとサブスクの違いは?
残価設定ローンは、契約時に数年後の残価(残存価値)を設定して、残価を除いた金額を返済するローンだ。3年後の残価が新車時の45%なら、残りの55%を3年間で返済する。
返済を終えても車両は自分の所有にならないが、月々の返済額は安い。そして返済期間満了時に、車両の返却、車両の買い取り、再びローンを組んで返済を続けるという選択ができるタイプが多い。
一方、サブスク(サブスクリプション)は、ローンではなく定額制のカーリースだ。借りて使うから、税金や自賠責保険料は月々の返済額に含まれる。
残価設定ローンも、返済期間満了後に車両を返却するとサブスクに近い使用形態となるが、税金、自賠責保険料、契約期間が3年間を超える時の車検費用はユーザーが別途支払う。維持費を含むか否かが最も大きな違いだ。
■それぞれのメリット・デメリット
残価設定ローンのメリットは、車両の買い取りなどが行えること。買い取り可能なカーリースもあるが、トヨタのKINTOなどを含めたサブスクには、買い取りできないタイプが多い。
基本的にローンは、分割返済した後、車両を自分で所有することを目的にする。そこに返却という選択肢を加えたのが残価設定ローンだ。
その点でサブスクは、借りて使うカーリースだから、返却が基本になる。つまり残価設定ローンは、サブスクに比べて利用する時の自由度が広い。
サブスクは使用後の買い取りなどができない代わりに、税金や自賠責保険料まで含まれた定額制だから、毎月の出費に増減が生じにくい。自動車税の納税通知書が郵送されて慌てて納めたり、車検費用を予め貯金する必要はない。
特に若い人は携帯電話を使い慣れているから、高い金額を支払って商品を買うのではなく、毎月一定額を納めて利用する感覚が強い。
残価設定ローンもこの消費動向に応えたサービスだが、税金や自賠責保険まで使用料金に含まれるサブスクは、その傾向がさらに強い。所有ではなく使用のニーズに応えたことがサブスクのメリットだ。
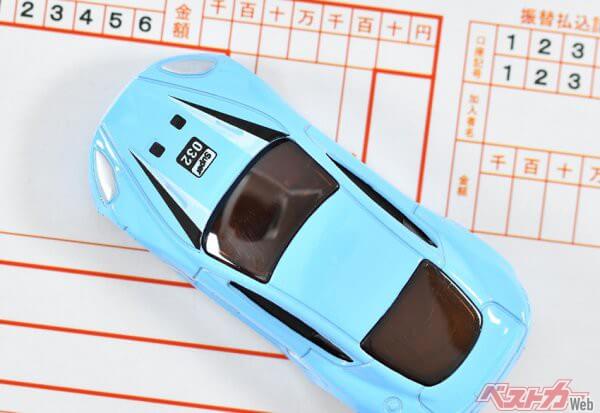







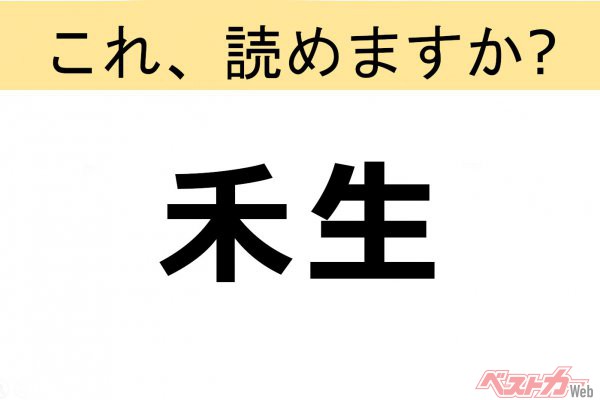















コメント
コメントの使い方