■最近増えてきた自転車専用通行帯を走行する自転車にクラクションを鳴らす
都内を走っていると、青く塗られた自転車専用通行帯を走る自転車に対し、遅くてイライラしたのか、邪魔に感じたのか、クラクションを自転車に鳴らしているクルマを見たことがある。
一般な知識として、むやみやたらにクラクションを鳴らしてはいけないと頭に入っているのだが、このケースは違反にならないのか?
道路交通法54条によると、自動車は見通しの利かない交差点や曲がり角などを通行する時、山道の見通しの利かない交差点や上り坂のてっぺんなどを通る時には、クラクションを鳴らさないといけないと書いてあるが、それ以外の状況ではみやみにクラクションを鳴らすと危険回避の理由がないかぎり、法令違反のおそれがでてくる(道交法121条1項6号、54条2項違反)。




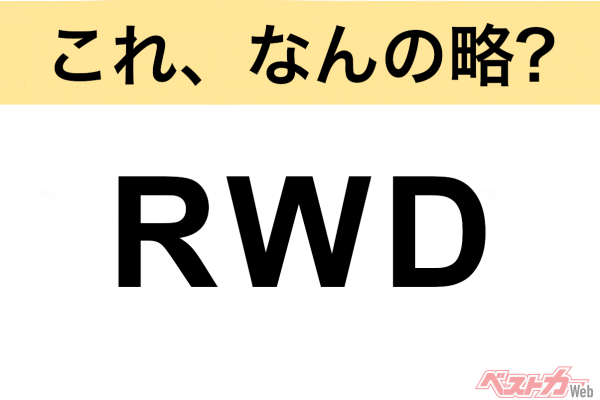














コメント
コメントの使い方自転車専用通行帯は実線で区分されているもので、写真は自転車ナビレーンです
自転車の通行位置を示すもので、ナビレーン内は原付や自動車も通行可能な車道扱いです
記事を書く前に、弁護士にでも確認して貰った方が良い。38条では、横断者が居るから分からない場合に、いつでも止まれるスピードで進行するとある。イケイケされて横断の意思が不明瞭なら、徐行で横断歩道を横切ればOK。警察官は、法律の専門家ではない。
>道路交通法54条によると、自動車は見通しの利かない交差点や曲がり角などを通行する時、山道の見通しの利かない交差点や上り坂のてっぺんなどを通る時には、クラクションを鳴らさないといけないと書いてあるが
標識ある場所だけだ
自転車にクラクション鳴らすのは、その接近で予想される危険を回避する為であることが通常だと思いますよ
勿論、クラクションに驚き転ぶ可能性まで様々に考えて使うべきですが、交通状況に気付いてなかったり危険な走行している相手に知らせるのは必要な場合も多々あります
クラクションを一切慣らさないことに慣れすぎて、必要でも使うのを躊躇うというのが一番よくない。クラクションは威嚇道具ではなく安全装備。有効な活用を
>それでは、横断歩道がない場所だったらどうだろうか? これは第38条の2に記載されており、「歩行者の通行を妨げてはならない」と定められている。つまり、横断歩道のありなしに関わらず、歩行者の通行が最優先ということなのだ。
これは誤りです。第38条の2をどう解釈すればこんな間違った解釈になるのでしょうか?
参考までに、道路交通法38条の2は以下の通りです。
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
つまり、「交差点」または「交差点のすぐ近く」で道路を横断しようとしている歩行者が居る場合、横断歩道が無くても車両等はその横断を妨げてはならないと解釈できます。これは、主に生活道路や郊外の道路の交差点を想定した条文と考えて良いでしょう。
横断しているときは