百年に一度の「モビリティ革命」が進むなか、本来であれば「日本の基幹産業を守る」という目標へ向けて一丸となるべきはずが、どうにもチグハグに見える日本自動車界と大手メディア。競争も大事だけど協調も重要、そんな思いから、「自動車界」と「経済界」の双方に詳しいジャーナリストの池田直渡氏に、脱炭素やBEV社会に関しては、なぜこんな誤解やすれ違いが起きているのか、どう理解すべきかを、丁寧に、骨太に、語っていただく短期集中連載をお届けします。まずは「第一回」の前編をお届けします。
文/池田直渡、写真/ベストカー編集部、AdobeStock
■「日本の産業界は、またもや同じ過ちを繰り返すのか」
「世界はすでにBEVに舵を切った。日本の自動車産業だけが井の中の蛙で、世界の変化を受け入れず、旧来の利権構造にしがみついている。新しいプレイヤーを否定しバカにしている間に置いて行かれる構造は家電業界で見たばかり、日本の産業界はまたもや同じ過ちを繰り返すのか」
まあ一般的世論と大手メディアの言いたいことは、だいたいこういう論調である。これに膝を打つ方はご用心めされよ、というのが筆者のスタンスである。
最近だいぶ差が縮まりつつあるが、上に挙げたような論を、自動車メーカー関係者や自動車ジャーナリストなど、業界内部の人は、たいてい苦笑混じりに呆れて見ている。
業界の人間は「地域特性とインフラ普及に応じてマルチパスウェイにしていく以外に、移動の自由を確保する方法はない」と考えている。
そしてたぶん、双方とも、相手がなぜそう考えるか理解できていない。そういう乖離がどうして起こったのか、考察してみたい。
■「クルマの価格は5分の1になる」という永守会長の無茶な予言
この記事の中では、一方を「メディア世論」、筆者を含むもう一方を「業界論」として進めよう。もちろん個人個人でそれぞれの持つ論には差異があるけれど、右にあげた論を両者の代表として二項対立で扱うことをご理解いただきたい。
ほんの1、2年前まで「内燃機関(ICE)は完全に消滅し、まもなく世界のクルマはすべてBEVになる」という「メディア世論」が世界に満ちていた。というよりそれ以外の意見はほぼなかった。筆者は、「マルチパスウェイ」を主張する少数派として一所懸命否定してまわったつもりだが、多勢に無勢でいかんともできなかった。
今でも忘れられないが、2019年、当時BEV専門メディアとして注目を集め始めていた「EV Smart Blog」が、米メディア「Clean Technica」の記事を翻訳して「2022年までにバッテリー調達コストが劇的に下がって内燃機関車(ICE)に優る競争力を獲得する」という、いくらなんでもスケジュール的にあり得ない記事を拡散した。
単純な話、当時どころか今でさえ、ICEに拮抗して販売勢力図を塗り替えるほどの生産量を持つBEV工場は、地球上のどこにもないし、仮に建設が奇跡的速度だとしても5年はかかる。5年で人の確保・教育までして稼働させるのはもう計画としては杜撰と言えるレベルである。
3年という短期間では物理的に不可能だ。だから「今にもBEVに市場を奪われてICEのマーケットが崩壊する」かのごとき針小棒大な言い方には苦笑いするしかない。
この無茶な仮説を受けて「EVネイティブ」などの動画系インフルエンサーが、これをあたかも「確定した未来」であるかのように、堂々と自信満々に言いきってさらにバズらせた。そういう意味では「業界論」側がSNSと大手メディア戦略で敗北したのは事実だと思う。
2020年には日本電産(現ニデック)の永守重信会長が「2030年にクルマの価格は5分の1程度になる」と発言。こうしたBEVの驚異的低価格化論がBEV信者以外にも拡散して、世の中にかなり間違った未来像を蔓延させたのである。
結果をみれば「Clean Technica」が予言した2022年はおろか、現在に至るまで、彼らのいうBEVとICEの価格均衡はやってきていない。
むしろ「リン酸鉄バイポーラ」を開発するなど、懸命にバッテリーの価格低減技術について発表と説明を繰り返しているのは、彼らがいう守旧派の頭目たるトヨタである。
![「ニッポンBEV出遅れ論」に見る大手メディアの節穴具合と実情 【短期集中連載:第一回[前編] クルマ界はどこへ向かうのか】](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2023/11/07161314/75d1cc7519b240ddf3a89d2c7b200432-600x371.jpg?v=1699341196)


![いまBEVが一般ユーザーの需要を「まともに」満たせるのは両極端だけ 【短期集中連載:第一回[後編]クルマ界はどこへ向かうのか】](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2023/11/07162217/3-600x344.jpeg?v=1699341739)














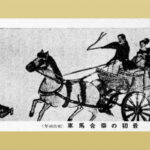





コメント
コメントの使い方池田さんや岡崎五郎さんらのように、唯一の正しい知見を元にきちんと意見発信してくださる方々を真のジャーナリストであると思う。特に、何かと叩かれがちなトヨタの姿勢を高く評価しかつ分かりやすく一般に説明されているのが素晴らしい。
聞いてるか日産、ホンダ。お前ら本当に日本企業か。正義はあるのか。
「ニッポンBEV出遅れ」って見出しの時、大抵電池の調達か車載OS(自動運転含む)の話題しかなくて、「この記者はクルマ乗らないんだろうな」と感じる。
例えばEVと言えばワンペダルだが、元を言えば油圧ブレーキと回生ブレーキの協調制御が難しいのを誤魔化すための技術だった。
トヨタが平然と実現してるから当たり前と感じるだけで協調制御がマトモにできてる会社って海外含めて今どのくらいあるんでしょうね?
BEV煽りや自動運転が直ぐだとか、現実的な資源配分、技術の充実には程遠い予測から、中国の安い資源を当てにした期待も梯子を外され、10年以内にバッテリーの革新が起きて家電並みに安くなるなんて事は起きてませんね。
シリコンバッテリー、アルミモーターが実際に市販車両に載るようになるまで、国の政策による乗り入れ規制、購買価格に対する多額の補助金に補助金まみれの充電施設まで置いて、ようやく形になる程度。
私は希望的観測も含めてICEは完全消滅しないと思っている者です。いずれBEVが主流になる時が来るかも知れませんが、それはここ5年10年の話では決してありません。今後ICEが存続する術としては、カーボンニュートラル燃料の普及が考えられます。今はまだ生産コストが高いそうですが、これが今のガソリンと同等か、より安く手に入るようになれば、焦ってBEVにしようと思うことなく今の車に乗り続けてていいのです。
素晴らしい記事。コメントより内容を読んでほしい。
これを前からある著名解説動画の焼き直しというのは簡単。でもジャーナリストとして責任ある立場で発信するのには様々な苦労があったはず。
ベストカーとして記事にしてくれた事をありがたく思いますし、これからも反撃にめげずに発信していって欲しいです。同志は沢山います。