■賃上げの背景には人材難が続く自動車メーカーなりの理由があった
実は自動車産業にとって、事はそう簡単ではない。今年の賃上げの口火を切ったのはまさに自動車メーカーで、他業界はそれに追随する形だったのだが、自動車メーカーには賃上げに動かざるを得ない理由があった。それは人材難である。
現在、自動車業界は通信、自動運転、カーシェアリング、電動化の4分野、すなわち「CASE」という100年に一度の変革が訪れるなか、世界的な研究開発競争が繰り広げられている。その戦いで勝ち抜くためには有能な人材はいくらでも欲しい。
必要な人材は多種多様。通信ではIT、自動運転では人工知能やセンサー、電動化では電気化学、カーシェアリングでは金融。もちろん、それ以外の分野でも高度人材は喉から手が出るほど欲しい。
が、クルマの変革を果たすのに必要とされるジャンルの人材は自動車以外の産業でも引っ張りだこ。しかも間の悪いことに、それらの産業をみると自動車よりずっと高いサラリーを出しているところが少なくないのだ。
■重要なのはメーカーや一次部品メーカーだけでなく、全体に賃上げを波及させること
クルマはもともと鉄鋼、電気、精密機械、化学、情報通信、半導体といった要素技術を寄せ集めて作るものだった。が、将来求められているクルマ開発には要素技術を買ってくるばかりではなく、自動車メーカー自身がそれらの要素技術に今までとは違うレベルで精通していることが求められる。
今春の初任給や賃金の引き上げで待遇面では異業種の優良企業に大きく見劣りしないレベルになったことで、とりあえず人材確保の第一関門は突破した格好だが、それだけではまだ不充分。この先はクルマが将来にわたって成長産業であり続けると働く側に感じさせるようなビジョンを経営者が提示し、それを実行に移していくことが大事だ。
もう一点重要なのは、この賃上げを自動車メーカーや一次部品メーカーなどの大企業限定ではなく、どうやって自動車産業全体に染みわたらせていくかということ。なぜなら自動車メーカーが人材豊富になっても部品メーカーが不人気のままではクルマを作ったり、技術を高めたりするのに支障が出るからだ。
コロナ禍以降、部品不足でクルマの生産が滞るという事態が長く続いた。その典型例は半導体だが、ハイテクの核となる先端分野のものではなく、単純かつ安価な素子だった。自動車メーカー関係者に話を聞くと、一様に「こんな小さいものがないだけでクルマが作れないなんて、頭では理解していても実感はなかった」と口を揃える。
そういう単純な部品を高品質かつ安定的に作る国内企業の多くはコストダウンの川下に位置するため、大なり小なり疲弊している。初任給や賃金を引き上げる余力はないが、引き上げなければ人材が来なくなるだけだ。
そういう企業が潤うためには、利益をしっかり出せるようなレベルの代金を自動車メーカーや上位の部品メーカーがきちんと払うことが必要であり、いわば企業を相手とした“賃上げ”のようなものである。中長期的にそれをやっていかないと、自動車メーカーは結局自分の首を絞めることになる。
■人材確保が喫緊の課題であるクルマ界
賃上げムードに沸く自動車業界だが、このように人材確保の課題は山積だ。大事なのは賃上げをインフレ対応の必要があった2023年に限定せず、今後も従業員には労働に見合うだけの賃金をきっちり支払うのが当たり前という感覚を経営者が持ち続けることである。
一方、労働組合も自分たちの労働の値付けをもっと高く見積もって経営陣に提示するという本来の仕事をちゃんとやらなければいけない。そもそも要求に一発で満額回答が出るなど、要求が低すぎたことの証でしかない。
経営陣も労働者も労働の対価に関する意識を根本から変えつつ、自動車が将来にわたって持続可能で成長性を見込める分野であると世間に見てもらえるようになれば、その時こそ自動車産業が本当に輝きを取り戻して羨望の的になることができるだろう。
【画像ギャラリー】2023年春闘は「満額回答」続出だが、自動車メーカーは「働き先」として羨望の的に復活するのか?(11枚)画像ギャラリー













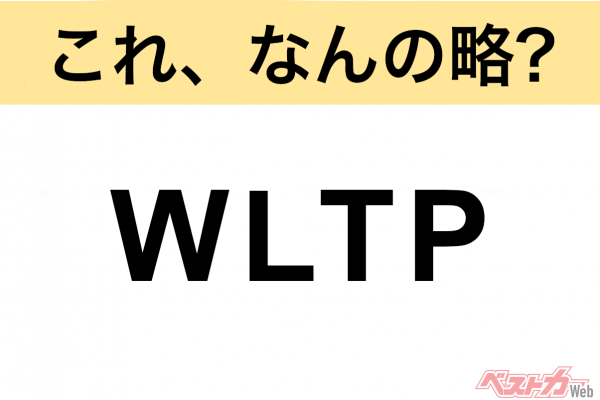




















コメント
コメントの使い方日産自動車のヤバさだけが際立ってしまったな。
役員の報酬だけは他社に負けてないんだが…