サマータイヤでもスタッドレスタイヤでも発生するトラブル、それが「パンク」だ。JAFの出動件数でも常に上位に入っている。
クルマのタイヤの性能は日進月歩で向上している。もちろん耐久性もだ。しかし、パンクやバーストは減ることがあまりない。なぜ、タイヤの性能が上がっているのに、パンクトラブルは減らないのか? 今回は、その事情について考察していきたい。
また、タイヤはモノによっては1本だけでも安い買い物ではない。そこで、パンクした際の対処法や、どのようなパンクならば修理可能なのかについても触れていきたい。
文/斎藤 聡、写真/AdobeStock(トップ画像=carbondale@AdobeStock)
■なぜパンクは減らない? タイヤの歩んできた歴史とパンクしないタイヤの現在地
ミシュランのマスコットキャラクターになっているミシュランマン=ビバンダムは、釘やガラス片をワイングラスに入れて飲み込むタイヤのモンスターとして描かれていました。1898年頃のポスターで、そこには「Nunc est Bibendum(すべてを飲み込む)」と書かれていました。
当時からタイヤと言えばパンクはつきものだったわけです。釘やガラスを拾って(踏んで)起こるパンクが多かったことも見て取れます。
実際、ミシュランの名声を一躍高めることになったパリ~ボルドー1000kmレース(1895年)で、ミシュランは世界で初めてが空気入りタイヤを装着したクルマで出場し、文字通り次から次へとパンクしたタイヤを交換しながら走り抜いたのでした。
これが実質的にクルマ用空気入りタイヤのデビューですから完成度が高くなかったのは致し方ないところですが、当時はタイヤの耐久性≒パンクは切っても切り離せないものでした。
これを大きく改善したのが米グッドリッチ社によるカーボンブラックを充填したゴムの開発でした。
カーボンブラックはゴムに充填することで補強効果を発揮して耐久性や耐摩耗性が飛躍的に向上します。カーボンブラックの生ゴムへの充填はイギリスのSCモートという化学者が発見し、これを米グッドリッチ社が実用化したわけです。
その後バイアスタイヤの確立、ラジアルタイヤの発明と、タイヤ構造・性能の進化とともに、タイヤはたやすくパンクしなくなっていきます。
興味深いのは、タイヤの西欧がある程度安定してからは、タイヤにとって天敵ともいえるパンクを防ぐ有効な対策がほとんど講じられていないことです。
特に現代クルマが普及してからは、パンクしにくいタイヤの開発はほとんど行われていません。もっとも大きな理由として考えられるのは、タイヤが消耗部品であるということです。タイヤ自体の性能が悪くてパンクするわけではありません、つまり製造者の責任は極めて少ないといえるわけです。
パンクする/しない、というのは運次第なところがあります。当然タイヤメーカーごとのパンクのしやすさに差はない(たぶん)ので、タイヤメーカー間でパンクしない性能を競う意味も見出しにくいというわけです。
むしろ自動車メーカーやタイヤメーカーの責任よりも、道路を管理する行政側の整備の問題も指摘できるわけで責任の所在が不明瞭なのです。
タイヤメーカーは、パンク対策に注力するよりも乗り心地や操縦安定性、最近では転がり抵抗や通過騒音の低減など、目の前の性能アップに力を入れなければなりません。これに対してパンク対策はさまざまな要因が絡み合っているためプライオリティが低いのだろうと考えられます。
もちろんパンク対策されたタイヤがまったくないのかというとそんなことはありません。近い将来登場する空気を必要としないエアレスタイヤはパンクしないタイヤです。ただ一般車への実用化はもう少し時間がかかりそうです。
また現在ある技術としては、パンクしても(一定の距離を)走行できるタイヤとしてランフラットタイヤやシールタイヤがあります。
ランフラットタイヤは、タイヤの空気圧が0プレッシャーになっても80km/hで80km走行できるように作られたタイヤです。ただし基本的にはリプレース用としては用意されていません。
現実的には装着は可能ですが、タイヤが重くなるので、サスペンションとのマッチングの関係で乗り心地が悪くなるケースがあります。またランフラットタイヤを装着する時は、空気が減っても普通に走れてしまうため、タイヤに空気圧センサーを取り付ける必要があります。
シールタイヤは、これも純正採用のみで市販では手に入らないと考えていいと思います。シールタイヤはトレッド裏側に粘着性の高いシール剤が塗布してあり、釘などがタイヤを貫通してもシール剤が穴をふさぎ空気の漏れを止めてくれるというものです。
というわけで、パンクにスポットを当てたタイヤの進化というのは、まだ一部車種に限定されているということです。







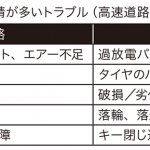



















コメント
コメントの使い方