F1好きなら誰もが『車椅子の闘将』フランク・ウィリアムズ卿のことを知っているだろう。自らF1チームを興し、プライベートチームながら巨大自動車メーカーを相手に数々の栄光を勝ち取ってきた。
そのフランク氏も寄る年の波と体調不良によりチームから手を引いた状態になっていたが、その後継者である娘のクレア氏が、2020年F1第8戦イタリアGPをもって、ウィリアムズ家がチームから手を引くことを正式に発表。
オールドF1ファンにとっては寂しい限りの事件と言える。ウィリアムF1の栄光と挫折について津川哲夫氏が考察する。
文:津川哲夫/写真:WILLIAMS RACING、ベストカー編集部
【画像ギャラリー】ピケ、マンセル、プロスト……e.t.c 懐かしのウィリアムズのF1マシンをフラッシュバック!!
気付けばF1での居場所を失っていた
車椅子の闘将、フランク・ウィリアムズ卿が率いるウィリアムズ・グランプリエンジニアリングは2020年イタリアグランプリを最後に、その経営の全てをアメリカの投資会社ドリルトン・キャピタルに譲渡。
これでF1業界に残っていた最後のプライベーターの魂が消えた。
その昔、フェラーリのエンツオ・フェラーリ、ロータスのコリン・チャップマン、ティレルのケン・ティレル……、皆一世を風靡したチームで、当時はどのチームも創始者の力と情熱が光っていた。
F1がまだレースに個人的な情熱を傾けるゲームであった時代だ。
もちろんフランク・ウィリアムズも1977年から43年に渡りその老舗プライベーターの席に着いていたのだが、半世紀近くを経てウィリアムズの周りを見れば、もはや純粋なプライベーターはF1に存続できない状況となっていた。
個人の資金で始まったF1レーシングも、時間の流れとともにパトロンが現れ、スポンサーの資金がレースビジネスを産み出し、近代化されたF1ワールドは大企業に席巻され、巨大自動車メーカーの覇権争いの場へと変わってしまった。
高度化された緻密なレースは近代人の感覚に添って、熱よりも情報が、肉弾戦よりも戦略管理が、泥臭い根性物語よりもスマートなITビジネス展開へと進化し続けてきた。
半世紀近くをかけて、世の中の潮流とF1はパラレルに進化をしてきたのだから、これは時代の変化として受け入れないわけにはゆかないのだ。
車椅子の闘将はまさに、この潮流に逆らい常に流れに竿刺してはきたのだが、近代化の巨大な大河の流れには逆らえず、一枚の木の葉の様に流されてしまった。
もちろんウィリアムズなりのレースビジネスは展開してきたものの、モダンな経営システムとメンタリティの近代化に乗り遅れ、古い暖簾を護ったことでデジタル世代が中枢を占める文化の進歩の速度に乗り損なってしまった。
ウィリアムズは現在のF1社会を築いた重要な一員であったはずが、ふと気がつくと、ウィリアムズは居場所を無くしていた。





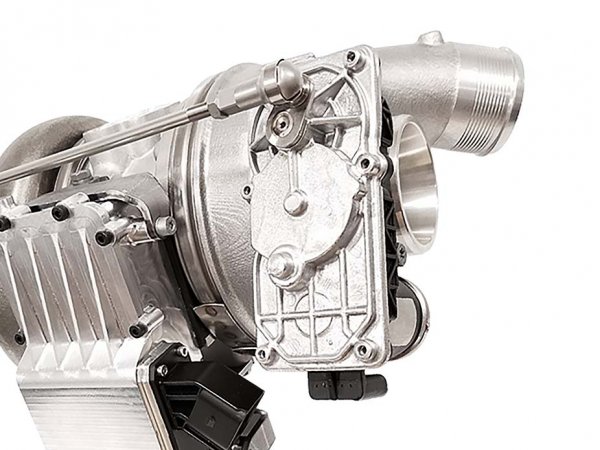



















コメント
コメントの使い方