■フェラーリルックを見事に消化!? エクステリア編
ニューシルビアはノッチバッククーペ、ワンボディである。やがて対米輸出用のファストバックモデルも加えられるかもしれないが、とにかくこのニューシルビアのスタイルはスポーテイでかっこいいと思う。
ニューシルビアのスタイルのポイントは”フェラーリルック″であることだ。ディノ246、BB、308/328と続いた一連のピニン・ファリーナフェラーリの特徴をうまくとらえている。
どこでそれとわかるかというと真横からが一番だ。フロントフェンダーの稜線はなだらかな丘のようだ。そしてその終わりにAピラーの下端と接する。
そこからはほぼ一直線にゆるやかにウエストラインが上がっている。このテーマはピニン・ファリーナがフェラーリで長く使っているものなのだ。
シルビアのスタイリストのうまさは、フェラーリルックをマネで終わらず、見事に消化していることである。それだからサイズも違う、条件も違うシルビアに違和感なく使えたのだと思う。
またウインドウ・グラフィックにも感動している。特にクォーターウインドウのスタイルがいい。だから斜め後ろからのルックスがとてもかつこいい。ニューシルビアのスタイルはあくまでスポーティカー。あるいはスポーツカーのものだ。
これがパーソナルカー流行りの現在の日本でどう評価されるか興味深い。しかし、このクルマはきっと街中へでると目立つと思う。低くて幅広く、それでいて、従来の日本流スポーティカーのスタイルであるロングノーズではない。
きっとこれを街で見たら新鮮だろうと思う。インテリアは外観のアグレッシブなスポーツ感覚とはまったく逆のソフィスティケートされたフランスタッチのものである。
そこにはシャープな角はひとつもなく、すべてRがついたデザインなのである。私はデザインとしてこのインテリアデザインを高く評価するがシルビアの場合、外観とは必ずしも合っていない。
やや刺激的なファクターの強いルックスと、まるで刺激性を感じないインテリアデザイン、どうもこれはしっくりこないのである。もし、このインテリアデザインをブルーバードに与えたら、あるいは新しくなると予感される。
プレーリーに与えたのならもう文句はない。メーカーの日産はこのシルビアについては、特に国内市場において、ソフトムードで売りたいと思っているらしい。
ホンダのプレリュードのビッグヒットを横目で見ての開発だからわからないでもないが、私はこのシルビアというクルマ、もっと本格的なものと受けとっている。
■どちらがお好き? ターボ付きorNAエンジン!
エンジンは2種。すべてCA18の1.8L、4シリンダーだ。ハイパワーはターボ対の170馬力、23.0kgmノンターボは135馬力、16.2kgmである。
ブルーバードはFFだからこの170馬カエンジンを与えるために4WDを採用せざるを得なかった。しかし、シルビアは後輪駆動なので苦もなくこのハイパワーを消化できる。
このヘんが後輪駆動のよいところだ。もし、このシルビアをベースにして3L、250馬力を与えようと考えたとしても可能性としては残されている。
さて、170馬カモデルのほうだが、ブルーバードより100kg以上軽いシルビアはそれこそ胸のすくような加速を見せてくれる。メーカー発表の0~400mは15.3秒、そのへんだろうと思う。
そして、その加速感である。後ろからグッと押されるフィーリング、この加速感こそがスポーツカーの楽しみだ。こいつを味わうとFFのハイパワー車はちょっと嫌になる。
エンジンは少々ノイジーだがレスポンスはいい。それとターボをまったく感じさせないのはすごい。どこからでもスロットルに敏感にレスポンスする。
このターボコントロールという点では日産の技術は頭抜けている。だから、逆にいうとナチュラルアスピレーションのほうはただのトルクの小さいエンジンに感じてしまう。
このナチュラルアスピレーションのほうもけっこう速く、おもしろいのだが、ターボと乗り比べるとどうということのないものになる。願わくばナチュラルアスピレーションのほうはもう500回転上のほうまで回るといい。
このCA18はややトップエンドが苦しいのが難点だ。ターボではそれはハンデとはならないが、ナチュラルアスピレーションではあと500回転が勝負どことなる。2Lを望む声もないではない。
後輪駆動を利して200馬力ぐらいまでは軽く消化できそうだから、しかし、私は現在の1.8Lで充分速く、軽快だと思っている。それに、このCAエンジンはとても軽いのだ。
この軽さがこの後輪駆動のスポーティカーにメリットとなっている。シルビアに乗ると後輪駆動車のもうひとつのメリットを思い出させてくれる。それはシフトフィールのよさである。
適度なストロークと節度感、これは楽しみといえるものだ。むろん、このスポーティカーはマニュアルボックスで乗ることを勧める。

![圧倒的な[275馬力]!! まさに[水平対向エンジン]よ!! しかも[DCCD]搭載!? 今見返しても[スバル インプレッサ WRX GC8]の作りこみレベチすぎじゃね!?](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2024/08/22171053/subaru_impreza-wrx_1994_wallpapers_1-1.jpg?v=1724314253)





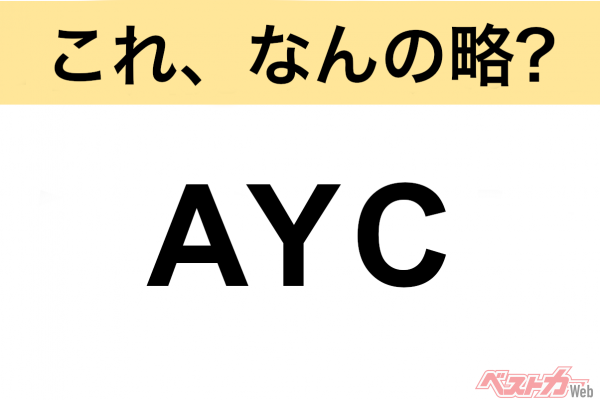

















コメント
コメントの使い方