変わった、変わらなかった部分とは?
正直に言って、自分が初代S30型(正確には2.4L仕様なのでHS30)のオーナーであるという強烈なバイアスがかかっているとはいえ、冷静に見ても初期のZ33型(先代モデル)の印象はさほど芳しくはなかった。
ドライバーの気持ちを鼓舞するような、スポーツカーに必要とされるオーラが不足気味だったのだ。
インテリアの質感や落ち着きのない乗り心地など、どこか中途半端な仕上がり具合に少なからず落胆したのを覚えているが、前述のように、続くZ34では多くの部分で不満は払拭され、たとえばこの Z50thアニバーサリーモデル でも19インチホイールを履きこなせているのは、その後の改良の成果といえる。
Z34型のスタイリングの魅力は、張り出したフェンダーなどのボリューム感が生み出す“マッチョさ”だが、パフォーマンスに関しては、全般的なレスポンスにはピーキーさはなく“紳士的”だ。
いっぽうで、実用性に富むといえば聞こえはよくとも、Z32型時代の世界レベルのスポーツカーを作り上げようという熱意はどうなったのかというファンもいるはずだが、個人的には「Zはそれでよい」という思いがある。それが見て取れるのが生産台数の推移だ。
■歴代フェアレディZの生産台数の推移
S30型(1969年10月~):48万4857台
S130型(1978年8月~):42万5403台
Z31型(1983年9月~):36万4691台
Z32型(1989年7月~2000年9月):16万5485台
Z33型(2002年7月~):23万6182台
Z34型(2008年12月~):12万2407台
合計:179万9025台
(※~2019年8月)
補足しておけば、日産が2002年に市場投入したZ33型は当初は追浜工場で生産されていたが、2004年1月からFR-Lプラットフォームを共有するスカイライン/フーガとともに栃木工場に生産が移管され、その後2011年1月からはZ34型が送り出されている。
こうして見ると、いかにS30型/S130型の存在が大きく、Z33型/34型がその恩恵を受けているかがわかる。
パフォーマンスの評価が高いZ32型が他の歴代Zよりも延び悩んでいることは意外に思えるが、あまりにも旧来のZファンにとってS30型からZ31型の印象が強すぎ、スタイリングなどに少なからず拒否反応があったのではないだろうか。
Z 50thアニバーサリーモデル と240ZGを比べてみる

初代から世代を経つつも受けつがれているものがあるかと問われれば「YES」と答えたい。
むろん、サイズ感と快適性が50年を時の流れがすっかり変えてしまっていることは当然の話だ。ホイールベースは初代の2305mmに対して、世代を超えて6代目では2550mmとなって、この差は当然ながら乗り心地にも影響する。
■初代S30ZとZ34型のディメンジョン比較
型式:全長・全幅・全高
HS30(240ZG):4305×1690×1285mm
Z34型:4260×1845×1315mm
S30型の全幅がボディの5ナンバー枠に収まる1690mmであり、標準仕様として14インチホイール(タイヤは前後:175HR14)を履いた場合、トレッドが1355/1345mmとなる。
対してZ 50thアニバーサリーモデルは全幅が1845mm、トレッドは19インチホイール(前:245/40R19 94W、後:275/35R19 96W)を装着して、1540/1565mmまでに至っている。
エンジンスペックを示しておくと、排気量2.4LのL24型SOHC直6の150ps/5600rpm、21.0kgm/4800rpmに対して、3.7LのVQ37VHR型DOHC V6は336ps/7000rpm、37.2kgm/5000rpmと、パワーとトルクで2倍前後も違うのだから比べるべくもない。
ただし、公表値として240Zの車重は1005kgと50周年記念車の1500kgとほぼ500kg(!)の差があることは(どちらもカタログ値)、スポーツカーとしての成り立ちを考えるうえで見逃せない。
ちなみに車両価格は240ZGが当時150万円。対して、今回のZ34の「50周年記念車」といえば458万8920円(6MT車、消費税込み)と、約3倍になるというのは個人的な半世紀の物価上昇のイメージに一致している。



















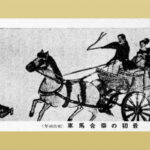



コメント
コメントの使い方