今年も年に一度の自動車税納付の季節がやってきた。自動車ユーザーの皆さんの手元にも自治体から「納税通知書」が届いているだろう。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今年は特定の条件(事業等に係る収入が前年同期比で概ね20%以上減少する等)を満たす場合、猶予制度も設けられているが、一般的に自動車税の納期限は5月末。今年は曜日の関係で6月1日となっている。
この自動車税、日本ではエンジンの排気量に応じて課税する仕組みを採っているが、少なくとも3万円弱、排気量によっては10万円超の課税額とあって、決して軽い税負担ではない。
考えてみれば、自動車税の大枠は様々な技術革新にも関わらず、長年変わっていない。日本の自動車税は果たしてこのままでいいのか。諸外国の制度も例にあげながら、清水草一氏が解説する。
文:清水草一
写真:ベストカーWeb編集部、TOYOTA、NISSAN
【画像ギャラリー】超重課税!? 排気量5L級超の現役国産車 5選
日本の“自動車税”は高いのか


5月は自動車税納付の季節。税額は軽自動車の1万800円から排気量6000ccオーバーの11万1000円まで幅広いが、登録車の場合、最低でも年額2万5000円(1000cc以下)支払う必要があり、痛税感は高い。
日本の自動車税制は、この自動車税(地方税)と重量税(国税)という、クルマを持っているだけでかかる「保有税」が高いのが特徴で、この部分だけを見ると、他の先進国の数十倍だったりもする。
ただ、欧州諸国は燃料税と消費税が日本の約2倍。トータルの税負担は日本より高い。
日本では、JAFや日本自動車工業会のキャンペーンにより、「日本の自動車税は世界的に突出して高い」というイメージが植え付けられているが、トータルの税負担は、欧州>日本>アメリカという順になる。
もちろん、保有税が高く燃料税が安い日本の自動車税制が正しいというわけではないが、完全な正解はないのも事実。
たとえば今年4月、日本総研にて、「自動車関係課税のあるべき方向性を考える」というレポートが発表された。
現行税制は税体系が複雑で課税の趣旨が明快でないため、それを抜本的に見直しつつ、税収が減らないように再構築し、「走行税」「重量税」「環境税」にまとめるという内容だった。
自動車税の「排気量課税」はもう古い?

それに基づいた税負担がどうなるかというと、乗用車は現在の4割減になるが、トラックやバスは現在の2倍以上。
理屈としては正しいが、これをすぐに実施したら、日本のトラック物流は壊滅的な打撃を受ける。もはやJRは貨物輸送を増やす余力に乏しく、経済活動全体が崩壊しかねない。つまり机上の空論である。
また、欧州のように保有税を下げて燃料税を上げると、持っているだけであまり乗らない傾向のある都市部の自家用車の負担は減り、クルマを毎日のゲタとして使っている地方部の負担が増えることになる。つまり、地方はさらに疲弊する。
こういった影響を考えると、自動車税の総額自体は、残念ながらあまり変えられないのではないか。見直すとしたら、現在は排気量ごとに決められている税額の区分のほうだ。
かつては、クルマの排気量は車格を表す最大の指標だったが、現在はハイブリッドやダウンサイジングターボの台頭もあり、時代遅れになっている。
では何を指標とすべきか。
候補に挙げられるのは、CO2排出量、馬力、車両重量の3つだ。
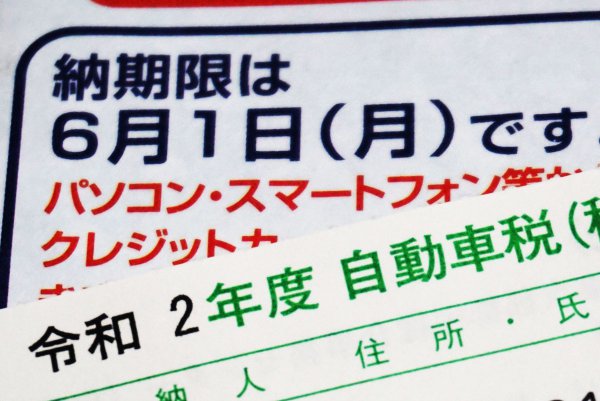

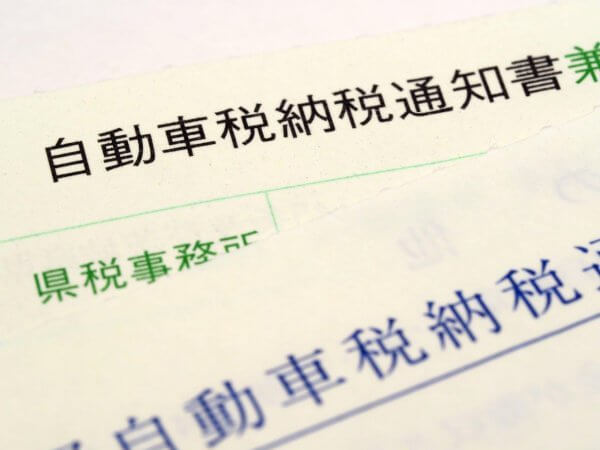















コメント
コメントの使い方