■一充電の走行距離の長さだけではない EVに対する各社の思惑
では、一充電で300kmというUX300eのEVとしての性能はどう判断すべきだろうか。
米国テスラ「モデルY」のパフォーマンスと呼ばれる車種では、一充電走行距離がWLTCで480km(推定値)とある。4輪駆動でより長い距離を走れるとされるロングレンジAWDという車種では、505km(推定値)だ。
ドイツのメルセデス・ベンツ「EQC」は、80kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載してWLTCで400kmである。
同じく欧州で発表されたマツダ初のEVであるMX-30は、35.3kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、WLTCで200kmといわれる。



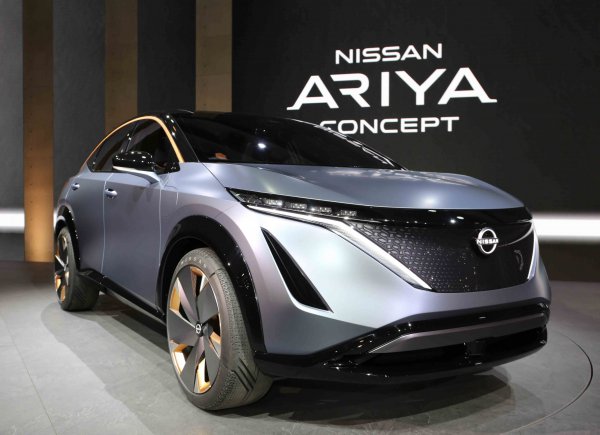
このように諸元を羅列しても、それぞれの性能がどの水準にあるのかみえてきにくい。そこで、搭載されたリチウムバッテリー容量を一充電走行距離で割り算をしてみると、WLTCを基準として1km走行するのに消費するおよその電力量を知ることができる。
計算結果は、UX300eが約0.18kWh(180Wh)/kmとなり、マツダ「MX-30」は約0.17kWh(170Wh)/km、そしてEQCが0.2kWh(200Wh)となる。モデルYは、搭載バッテリー容量がわからないため計算していない。
いずれにしても、1kmを走るのに170~200Whといったほぼ近い数値の消費電力量であり、各自動車メーカーが可能な限りの効率の追求を行っている様子がわかる。そのなかで、日本の2社はより少ない電力でWLTCのモード走行ができているといえるだろう。
ただし、リチウムイオンバッテリーの搭載量が増えればその分車両重量が重くなり、必ずしも電力量が増えた分がそのまま距離の延長につながるわけではない。またEQCがモーター2個を搭載して4輪駆動であるのに対し、UX300eとMX-30は1つのモーターで、前輪駆動であることから、モーターや駆動系の重量もEQCより軽く仕上がっているはずだ。エンジン車でも車両重量が重くなれば燃費が悪化するのと同じで、重い分だけ電力消費量が増え、距離の伸びは鈍る。
そこを、マツダやレクサスは視野に入れながら、できるだけ少ないリチウムイオンバッテリー搭載量で、消費者が納得できる一充電走行距離を模索した結果であろう。

それでも、テスラが480kmと長距離を求め、EQCも400kmは確保した。そこについては優劣ではなく、消費者の選択肢と理解すべきだろう。日常的な利用でそこまでの距離を求めないのであれば、余計なバッテリーの搭載は、重量増による電費の悪化と、車両価格の上昇につながる。ことに欧州の人にとっては、バリュー・フォア・マネーというか、合理性を、買い物の際には重視する傾向が強い。





















コメント
コメントの使い方