■低所得層へのアピールとして格安EVもアリか?
日本では、大排気量車といえばお金持ちが乗っているイメージが強いが、アメリカではいまも、新車購入するためのローンやリースの審査が通らずに、中古車しか買えない層(おもに低所得層)が多く購入している。
昔ほどではないものの、年式が古く排気量が大きいだけでなく、環境性能も劣っている車両(結果的に値落ちも早いのでアメリカンブランド車になりやすい。日本車は中古車で購入するのも価格高めで簡単ではない)を保有する傾向が目立っている。
現状ではBEVやPHEVはもとより、HEVすらガソリン車より車両価格が高いのが現状。そして、いま世界的に騒がれている車両電動化の主役はBEVとなるので、同クラスガソリン車との価格差はより大きくなっている。
仮に補助金を手厚くしたところで、その差が縮まる程度であり、そもそもアメリカでは新車購入はローンかリースを組むのが大原則なので、低所得層はまず審査自体が通らないだろう。
富裕層から電動化を進め、ややタイムラグがあるが中古車で、低所得層にも普及をはかればいいだろうという意見もあるだろうが、日本とはクルマについて、レベルの違う酷使をするアメリカで、果たして中古車のBEVのコンディションがどうなっているのかも気になるところ。
買ったクルマのマイナートラブルで電池交換となっても支払うことができるのだろうか?
ミシガン州デトロイト及び近郊のフリーウェイを走っていると、道端の大きな看板に「クルマを寄付してください」と書かれたものをよく見かける。
デトロイト市及び近郊でも当然ながら路線バスは走っており、以前より車両も新しくきれいになったが、日本のように時刻表があるわけでもなく、バス停で待っていてもいつくるかわからないというのが現状。
結果的にデトロイトあたりの都市でも乗用車がないと生活していくのが大変なのである。しかし、クルマを買うお金のないひとも多く、“クルマの寄付”を募っているのである。この“寄付”となると、少々風向きが変わってくる。
例えば、中国系というと現状では米中対立もあり難しいかもしれないが、アメリカ国内のBEVベンチャーが、一時話題となった中国の上海通用五菱汽車の45万円ほどの格安BEVに近いものを開発し、これを宣伝も兼ねて低所得層低所得層向けに寄付してしまうというならば、普及に弾みがつきそうだ。
■日本でも『自動車所有難民』が出現する
日本でも“格差社会”というものが叫ばれて久しくなってきている。
新型コロナウイルス感染拡大以降さらに顕在化しているともいわれている。日本についてはあえて“生活困窮者”とさせていただくが、そのような所得の低いひとたちには、格安で買え、維持費負担も軽い低年式(古い)軽自動車の中古車が現状では受け皿となっている。
大手中古車検索サイトをみると、年式が2000年代前半で10万km以上の走行距離の軽自動車が多数掲載されている。ただ、日本でも経済産業省が2030年までにガソリン車の販売終了を検討しているという報道があり、いまやそれが既定路線となっている。そして、現状では軽自動車も例外ではないとされている。
軽自動車では一部の車種では現状でも、簡易式のHEVのラインナップはあるが、フルHEVやPHEV、BEVなどはラインナップされていない。当然、軽自動車もHEVやPHEV、そしてBEVなどのラインナップを進めるのだが、当然ながら価格上昇はまぬがれない。
現状ガソリン車でも支払い総額で200万円付近が当たり前の軽自動車(新車の場合)が、いま以上割高となれば「新車で軽自動車も買えない」という層が増えていきそうである。
販売終了について中古車販売は含まれていないようなのだが、いまの世界的な脱炭素社会の動きを見ていると、その“猶予”がいつまで続くのか不安が残る。
政府が負担軽減のため、電動車購入のための補助金をいま以上に手厚いものにしないと、全体で見ても普及はなかなか進まないだろう。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大に関する財政出動では、庶民が実感あるかないかは別として、世界でもトップクラスの税金投入をしたあとなので、あまり期待できない。
結果的に、新車で電動軽自動車すら購入できないひとが増え、そのようなひとたちが中古車購入(ガソリン車)に流れるが、新車販売の(トルツメ)販売が不振になれば、当然下取り車も少なくなり、中古車のタマ(在庫)不足が発生。
そのなかでタマの奪い合いも起これば中古車価格が上昇し、そのために生活困窮者への負担を増やしかねないだけでなく、電動車普及もなかなか進まないことになりかねない。
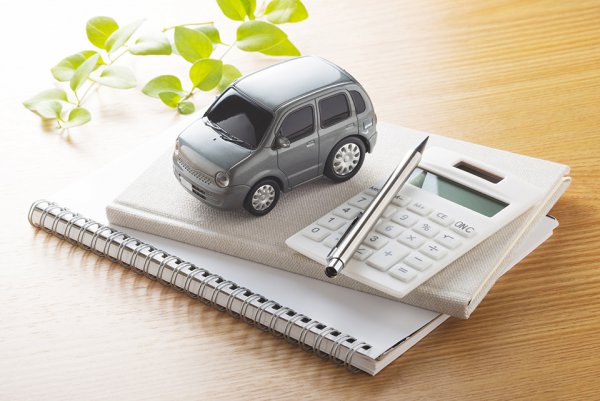
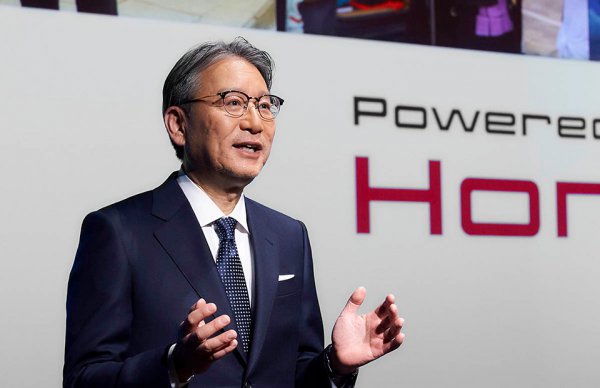

















コメント
コメントの使い方