値上げラッシュの原因は?
各メーカーが車両の価格改定に踏み切るのは、主に以下が原因となっている。
●原材料価格の高騰
●エネルギーコストの増大
●輸送費の高騰
ロシアのウクライナ侵攻後、世界的な物価高が続いているのはご存じのとおり。
特に、車体各部に使用されるアルミ、マフラーの触媒となるパラジウム、バッテリーに不可欠なリチウムなどの採掘資源は、原産国としてロシアが高いシェアを誇ることもあり、2022年には異常ともいえる高値を記録した。
しかし、2022年11月頃にはどれもがピークアウトし、2023年5月時点では多少落ち着きつつある。ただし、数年来の相場においてはいまだ割高な状態にある。
原油価格も同様に、2022年のピーク以後は徐々に価格を戻しつつある。
ただし、採掘資源や原油の高騰は、時間差をもって製品価格に反映されるため、この数カ月における各社の車両価格の改定は、2022年秋にピークを迎えたそれら資源価格の影響が、タイムラグをもって表出した結果だといえるだろう。
国内の各自動車メーカーは、あらゆる手を尽くしてコストの圧縮に努めているが、コストの増加分を吸収するにはすでにその限界を超えている。
実際、過去においてはモデルチェンジに合わせて価格改定を行うのが国内車両メーカーの通例だったが、それを待たずに値上げを実施するという異例の事態が相次いでいることからもメーカーの苦境がうかがい知れる。
トヨタも値上げに踏み切るのか?
こうした状況のなか、トヨタはこの半年間、価格改定を行わずに耐えてきた。しかしトヨタは2023年の上期(4~9月期)に、一次取引先からの調達品購入価格を引き上げることを表明している。
これは主に、日本製鉄からの鋼材の買取価格の値上げを了承したことを意味する。つまり近い将来、そのコストが車両価格に反映され、トヨタ車においても値上げが実施される可能性は高い。
トヨタは協力会社の経営安定化を図るため、電力やガスなどのエネルギー費用をトヨタが負担することまで検討している。同社は価格改定を極限まで引き延ばしつつ、さらにはサプライチェーン全体の存続にも注力しているのだ。
スズキは、海外市場においては車両価格の値上げをしてきたが、国内においてはやはり価格の据え置きを維持してきた。
しかし、2023年5月15日に行われた決算会見の場で鈴木俊宏社長は、近い将来において全車種値上げする可能性を示唆、その苦しい状況を明かした。
苦しいながらも5割が増収増益
各社とも車両価格の改定を実施、またはその決断が迫られてはいるが、その経営状況は決して悪くない。
2023年4月後半から5月にかけて、国内自動車関連メーカーの決算が続々と発表された。それを集計したマークラインズ社のデータ「国内の自動車メーカーと部品サプライヤー各社の通期(2023年3月期)決算まとめ」(5月22日現在)を見ると、主要メーカー(OEM社)9社と、主要サプライヤー67社、計76社においては以下のような決算状況となっている。
●増収増益/38社
●増収減益/36社
●減収増益/0社
●減収減益/2社
つまり、76社中の2社以外はすべて増収であり、全体の半数は増益でさえある。
ただし、この数字が比較対照する2022年の同時期は、ウクライナ戦争の勃発によって世界的な情勢不安が高まった頃であり、かつコロナ禍でもあったため、今期(2023年)においては好成績が出やすい状況にあったともいえる。
また、昨今続く円安によって、各社とも海外事業の成績が好調だったことも影響している。






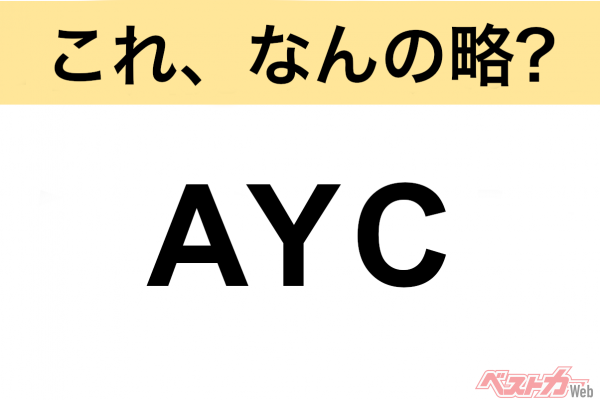

















コメント
コメントの使い方