1980年代以降日本で人気の高かったリッターカーだが、現在日本車で1Lエンジンを搭載しているのはトヨタ車、ダイハツ車のみだ。
リッターカー全盛時代には、いろいろな個性派が登場して楽しませてくれた。現在ではスイフトスポーツをボーイズレーサーと呼びたいが、その言葉自体もはや死語と化しているのは寂しい限り。
街中やワインディングを運転して楽しい、小気味よく走る、そして競技にも使えたといいう日本の個性派ボーイズレーサーを紹介していく。
文:片岡英明/写真:TOYOTA、DAIHATSU、NISSAN、SUBARU
【画像ギャラリー】今の時代にこそ復活してほしい!! 日本人が愛した個性的なボーイズレーサーをじっくりと眺める
トヨタパブリカ・スターレット(初代)
販売期間:1973~1978年(1973年10月にスターレットに改名)
マイカーブームの火付け役だったパブリカの流れを組むコンパクトファミリーカーがトヨタのスターレットで、その証拠に1973年春にデビューしたときは「パブリカ・スターレット」を名乗っている。
クルマに興味旺盛なエントリーユーザーを狙い、最初は2ドアモデルだけの設定だった。スタイリングも2代目のパブリカより若々しい。
「バレットウエッジ」と名付けたロングノーズにファストバックのキュートなフォルムで、ベルトラインを一段低くしてガラスエリアを広げている。この美しいデザインを手がけたのは、イタリアの鬼才、ジウジアーロだった。
売りのひとつはセリカと同じようにフリーチョイスシステムを採用したことだ。エクステリア、インテリア、エンジン、トランスミッションを自由に選ぶことができた。
ラリーカーをイメージしたSRには精悍なRインテリアが、主役のSTにはゴージャスなG、ラグジュアリーなL、スポーティなSと、3つのインテリアを設定している。
エンジンは993ccの2K型直列4気筒OHVとカローラから譲り受けた1166ccの3K型だ。秋には4ドアモデルが追加され、この時に「スターレット」と改名した。
特筆したいのは、ツーリングカーレースで勝つためにスペシャルモデルが用意されていたことである。注目の心臓は排気量を1293ccに拡大し、DOHC4バルブヘッドを架装した3K-R型だ。
富士スピードウェイで開催されているマイナーツーリングレースではサニー1200クーペと熾烈なバトルを繰り広げ、1974年から3年連続してシリーズチャンピオンに輝いた。
今なおレースファンから語り継がれている名車が、初代のKP47型スターレットだ。


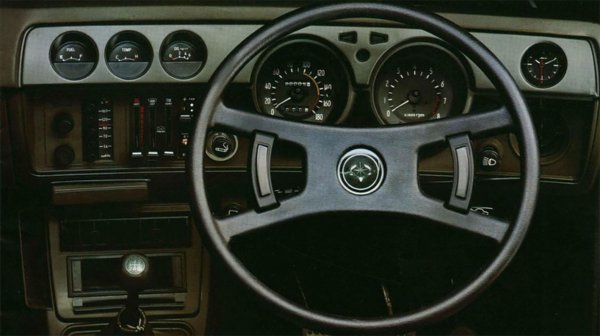


















コメント
コメントの使い方