SUV(スポーツ多目的車)への注目が集まっている。例えばトヨタは、ヤリスクロスとカローラクロス(ただし、タイにて)を相次いで発表した。
2019年はRAV4が復活し、販売が好調だ。ハリアーも根強い人気に支えられている。C-HRは頻繁に目にするほどの人気だ。ダイハツとトヨタから発売された、ロッキー/ライズの好調も続く。
日産は、2020年6月にe-POWER専用車種としてキックスを新発売し、2020年内の納車が間に合わないほどだという。
ホンダヴェゼルは7年目に入ってなお、存在感がある。
軽自動車でも、スズキのハスラーが2代目となり、ジムニーもベスト15位以内に入り健闘が続いている。ダイハツからは、タフトが誕生した。
輸入車に目を転じても、東京近郊で目にするのはSUVばかりといって過言ではない。しかし、これがブーム(流行)であるのかどうか? またブームならいつまで続くのかについて考察していく。
文:御堀直嗣/写真:TOYOTA、NISSAN、HONDA、MAZDA、SUBARU、MITSUBISHI、SUZUKI、DAIHATSU、PORCHE、GM、佐藤正勝、池之平昌信、ベストカー編集部
【画像ギャラリー】トップ50に18台がランクイン!! 2020年8月のSUV販売ランキング
SUVばかりが売れているわけではない
SUVがブームかどうかを検証するにあたり、まずは販売動向を見てみよう。
一般社団法人自動車販売協会連合会の乗用車ブランド通称名別順位によれば、2020年1~6月の1位は5ナンバーSUVのトヨタライズである。これに、同じクルマであるダイハツロッキーを加えると、販売台数は7万5884台となり、半年間に毎月1万2000台以上が売れたことになる。SUVの中でも、小型SUVの人気が高まっている証だ。
いっぽうで、2位以下の車種をみていくと、カローラ、フィット、ヤリス、ノートの順で、カローラは3ナンバーだが5ナンバーに近いセダン、ステーションワゴンと、5ナンバーのハッチバック車が上位を占めているのである。
さらに10位までを見ても、シエンタ、フリード、ルーミー、プリウス、アルファードの順であり、コンパクトミニバン、ハッチバック、大型ミニバンというわけで、SUVの車名が顔を出していない。
15位にRAV4、19位にC-HR、20位にヴェゼル、24位にマツダCX-30という状況で、堅調な売れ行きを続けているが、消費者の購買意欲がSUVばかりに偏っているわけではないことがわかる。





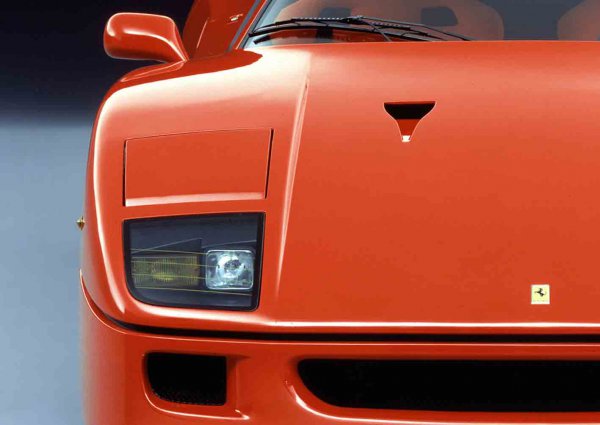


















コメント
コメントの使い方