長年日本の4WDを支えてきた三菱パジェロの国内生産が2019年8月いっぱいで終了する。非常に寂しいものの、現行パジェロは2006年の登場以来すでに13年目とメカニズム的にも古さは隠せない。
いっぽうのこちらもアメリカン4WDの生き字引であるジープラングラー。ラダーフレームを採用するなど伝統を重んじたモデルだが、まだまだ進化が続いているモデルだ。
日米の名門4WDを今回、元日産エンジニアにしてR35 GT-R開発責任者の水野和敏氏に試乗してもらいました。尖った性格のこの2台、水野さんは箱根のワインディングでどのように評価するのでしょうか?
ベストカー本誌連載『水野和敏が斬る』をノーカットでお届けしよう。
文:水野和敏/写真:池之平昌信
ベストカー2019年8月26日号
■ 「何にでも幅広く対応する」 が選ばれない時代になった
皆さんこんにちは、水野和敏です。
今日は楽しみな取材です。隙もなく精巧に作られ”こう乗りなさい”と、枠がはめられているようなドイツ車とは対照的に、アバウトだからこそ自由を感じるアメ車が私は好きです。
しかも、今回はこれぞアメリカンSUVともいえるジープラングラー。その向こうには、荒々しい岩が突き出る山岳ダートと雄大な国立公園が見えます。

一方、パジェロはこれが『ファイナルエディション』ということで、2019年8月をもって国内での販売を終了すると聞きましたが、一瞬、マークX同様、時代の流れを感じます。
私は講演のなかでも言っていますが、ITやSNS情報が蔓延している現代では「合理性の賢さ=使い捨て消費型」や「優越感=ブランドや自己占有型」の要素がない商品、つまり、ひと昔前では主流だった「自己満足」を満たすのみで「何にでも幅広く対応する」という”中途半端”なものは行き場所を失っているということです。
誤解をしないでいただきたいのですが、ちょっと前まではその”中途半端”なものが”ジャストフィット”だったのです。
SNSなどの発信情報がなく、ヒエラルキーの階層を認めて、各人が分相応に生活していた時代ではオールマイティさ(何でもできる)ということは、まさに適応性や利便性でした。
しかし裏を返せば「個性の薄い中途半端な商品」ともみられます。
例えば、ひと昔前であれば憧れの的だったマークⅡやスカイラインなどは、ITやSNSの氾濫した情報が否応なしに作り上げた「比較する・自慢する・主張する」現代文化のなかでは”中途半端”な存在感となってしまったことは否めません。
少し無理してでも、国産であればクラウンやレクサス、輸入車小型セダンならベンツやBMWを買えばブランド性やステータス感が持て、自慢や主張ができます。
また、SUVであれば「個性や買う意味」を難なく主張できますし、SUVはVRゲームのように個性的に進化しています。
一方、賢く合理的な選択の自己主張では「軽自動車やハイブリッド、コンパクト多機能車」が売れるという現象もあります。
この中間でどちらにも属せないマークXやスカイラインは、「ちょっとフォーマルで、少しラグジュアリーで、スポーティな走りや気分も味わえる、5ナンバーサイズで価格もリーズナブル、家族も乗れる」といった1980〜1990年代の”自己満足の完結”型の世界であれば、まさにこのオールマイティさが憧れでした。
しかし「比較する、自慢する、主張する」IT・SNS文化の現在では”中途半端”的な存在となってしまったのです。
パジェロもまさにそんな時代の日本で生まれたクルマです。オフロードもそれなりに走れるタフさ、クロカン車と実用ワゴン車の中間で違和感がないデザイン、国内の道に合ったボディサイズや乗り心地、日常の家族旅行にも使える室内空間とリーズナブルな価格。
ランクルのような本格クロカンではなく、SUVほど個性や主張がなく、やはりオールマイティを狙ったクルマです。
ジープラングラーのように、スパルタンでアメリカの岩が突き出たガレ場の荒野をグイグイ走るためのクルマとは違います。
ラングラーはオフロード性能に特化させた半面、日常での使い勝手や快適性やラグジュアリー感はスッパリと切り捨てています。

そういった意味で、パジェロは”中途半端”感のあるクルマと言ったのです。
これはクルマにかぎらず、ものを選ぶ時全般に当てはまります。以前は自己満足の世界だったものが、現代では他人との「比較、自慢、主張」が重視されています。SNSやインターネット社会が作り出した現実です。
食事だってそう。以前だったら自分が食べておいしければそれでよかった。でも今はSNSにアップし自慢して”イイね”がほしい。
クルマ選びもその視点がより強調されてきています。オールマイティなものよりも、何かに特化された、ある意味尖った商品が求められるようになっています。

















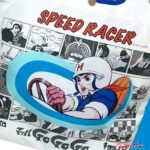




コメント
コメントの使い方